休職してしまう学校の先生が増えています。
全国に学校はいくつもありますが、
1校に一人以上、休職している先生がいるのも珍しくないです。
本来クラス担任ではない教頭が、
休職した先生の穴を埋めるために担任をすることもあります。
この危機的状況はなぜ止まらないのか?
いくつか原因はありますが、一番の原因は職場の管理職や同僚の教員だと思います。
・病気休暇(休職)の現状
・人間関係が病気休暇に与える影響
・辛い環境から抜け出す方法

もし、現在教員として働いている方に読んでもらえていたら、
「この辛さは自分だけじゃなかったんだ」
と少しは気が軽くなるような記事にしていきたいです。
今とても辛い思いをしていて、
すぐに相談がしたい、自分の症状の診断をしてもらいたいという人は、
オンラインクリニック「かもみーる」をご利用ください。
心療内科の先生が優しい気持ちで話を聞いてくれます。
職場にいることがつらくて、
今すぐ退職を考えている人は、
退職代行サービスを利用することも1つの方法です。
また、筆者がオンラインカウンセリング(クリニック)を利用して、
病気休暇を取得し、気持ちが楽になった体験を記事にしているので、
合わせてこちらもご覧ください。
【筆者について】
名前|きくみち
小学校、特別支援学校で勤務経験あり。
初任校でパワハラを受け、一度学校を離れる。
HSP気質。
頭痛、吐き気の症状が出てきて、病気休暇に入る。
教員の病気休暇率と負のサイクル

病気休暇(略して「病休」)とは、健康上の理由で仕事を休む際に申請する休暇のことです。
文部科学省は、平成29年から令和3年までの5年間を通した、精神疾患による病休を取得した教員の数を公表しています。
これによると、令和3年度の病休の人数は過去最多とのことです。
また、担任をしている教員が病休になると、新たに担任をしてくれる教員を配置する必要が出てきます。
ただ、教員の数が足りず、他の教員複数でその学級を取り持つ状態が増えてきています。
なかには、新しい担任が見つかっても、続けることが困難になり、
1年で4回も担任が代わった例もあるようです。
教員が減る→各々の負担が増える→体調を崩す→教員が減る
という負のサイクルとなってしまっています。
教員の病気休暇と長時間労働

まず、世間で一番問題視されている、教員の長時間労働との関連性から、病休について考えていきます。
教員の仕事量
教員が長時間労働をしなくてはいけない理由は、
一人一人が抱えている仕事量が勤務時間内で終わらないほど多いからです。
そうはいっても、文科省から義務づけられている必要性を感じないもの、
校長の各教員に課す仕事分担が下手、表面上の会議のためだけに資料を用意する等、
様々な要因があることも事実です。
また、授業準備など個人の裁量に由るところでは、
パソコンを使わず手書きにこだわって業務量が多くなるなど、有効性を考え直す働き方も存在します。(その教員は無理がたたって倒れてしまったとのこと。)
長時間労働の影響
では、長時間労働が病休を増やす一番の原因であるかというと、私はそうは思いません。
確かに、誰でも長時間労働は嫌です。
家族との時間を取れないし、趣味の時間も取れません。
土日も勤務している人もいますからね。
もちろん、休憩が取れずに、体に負担がかかり、体調を崩す人もいます。
ただ、教員をやりたくない、退職する理由としては大きいですが、
病休までいくかということを考えると、少し違う気がします。
教員として働いている人のほとんどは、長時間労働を覚悟の上で勤務しています。
また、教員として働くことを楽しんでいる人は、長時間労働でも元気が持続する人ばかりでした(そういう人達だからこそ続けられるということもありますが)。
当たり前ですが、そういう人達も仕事に対して文句を言うことはあります。毎日です。
職員室の様子
ただ、「子どものためになる」と思えるような業務には時間をかけてもやるべきだ、
と考えている人が多いので(むしろそれが楽しい?)、
勤務時間オーバーを仕方ないと捉えていました。
あとは、何人かの教員で一緒に作業をすることもあるのですが、
特に年代が近い教員同士だと、夜遅くでも楽しく喋りながら作業することもあります。
私が教育実習でお世話になった実習校の先生は、初任の頃は夜21時退勤だったけど、同僚も同じ境遇だったから続けられたし苦ではなかったと話していました。
あくまで私が勤務していたときの印象ですが、
同僚と仲がよかったり、教員であることに自信を持った状態で、効率のいい仕事の進め方ができれば、病休の大きな原因にはなりにくいかなと思いました。
同僚と仲がよければ、辛くなる前に助けてくれもしますからね。
心配の声かけをしてくれたりなどもありました。
裁量と責任の大きさと教員の病休

次は、裁量と責任の大きさとの関連から、病休について考えていきます。
学級担任の責任
日本は基本的に担任は一人です。
そして小学校は特に、担任が自学級の授業を行うことが大半です。
自分の行いで学級の児童生徒の全てが決まってしまう。
隣についてくれる人もおらず、何かあったときは全て自分の責任です。
自分の目が教室全体を見れていればまばいいものの、
体調を崩した児童を保健室に連れて行ったり、清掃時間に見回りに行っていた際にトラブルが起こることなど往々にしてあります。
トラブルの内容や程度によっては保護者に電話する必要も出てきます。
教員に成り立ての人は特に、「研修やルール化されていることが少ないのに、ここまで自分に責任を押しつけられるのか」と思ってしまうでしょう。
学級担任のプレッシャー
また、私もそうでしたが、「担任である以上1年間は勤め上げなければいけない」
というプレッシャーは大きいです。
一般企業でも4月~3月で一区切りかもしれませんが、
担任が途中で代わったら、児童生徒に大きな迷惑がかかる、
という思いがある以上、途中で降りてはいけないという意識はかなり強いです。
そのため、本当は仕事が辛くて途中で辞めておいた方がいい状態なのに、
児童生徒に迷惑はかけられないと我慢を続けてしまい、
結果体を壊してしまうということは大いにあります。
こうなる前に、辛くなったらまず1,2日休むことがいいですね。
その日は他の教員の負担にはなりますが、病休になるよりは絶対にましですから。
またこういう状態も、同じ学年の同僚が助けることはできますし、
同僚の仲がよければ「多少の失敗は許容範囲」という雰囲気も作れるので、
プレッシャーを減らすことができます。
児童、生徒の関係と教員の病休

3つめに、児童、生徒との関係性の関連から、病休について考えていきます。
児童生徒対応の負担
当たり前ですが、学級には教員の注意を頻繁に受ける児童生徒が何人かいます。どこでも笑。
だから教員もストレスがたまります。
けれど、それだけで病休になることはほとんどないです。
ただ、いわゆる”荒れている”学級や学校では、心身の負担が大きくなります。
こちらが手を尽くしても、改善しないどころか悪化していく場合が多いのではないでしょうか。
ひどいときには自分に向けた罵りの言葉を言われたりします。
それが原因で病んでしまったり鬱になる場合もあります。
児童生徒対応の影響
ただ、これも病休に入ってしまう要因ではありますが、
大きな割合を占めるかと言われれば、そうではない場合の方が多いのではないか、
と勤務した経験から思ってしまいます。
学級や学年が荒れていたら、学年の教員が一丸となってその対応を考えますし、
問題となってる児童生徒には他の教員も注意深くみていく体制をとっていきます。
教員同士が協力し合えれば、
児童生徒の問題行動に耐えられず後ろ向きになるということは案外多くない印象を持っています。
私が直接聞いた話ですと、代々荒れているで地元では有名な小学校に勤めていた方は、
授業が成り立たないくらい荒れていて、児童の対応には手を焼いて苦労が絶えなかった職場でした。
しかし、教員同士は仲がよくて働きやすかった、とおっしゃっていました。
なんでも教員同士で休日にバーベキューに行くくらい仲がいいとか。
保護者との関係性と教員の病休

4つめに、保護者との関係性の関連から、病休について考えていきます。
保護者対応の負担
一時期よりはメディアで取り上げられることは少なくなりましたが、
モンスターペアレントと称されたように、保護者からのクレームは多くあります。
児童生徒の下校後に、まずは保護者対応でやるべきことを片付けるというように優先順位高めで仕事をする教員も多いのではないでしょうか。
教員によって態度が変わる
私の場合は、受け持った児童の親から、
前年に「女性担任と合わないから次年度は若い男性を担任にしろ」と要望があったようです。
また、私は男だったので、保護者面談などで児童の母親達にかわいがってもらっていたと思いますが、若年女性教員のなかでは、「子どもを育てたことがない人に教育の何が分かるの?」
と言われた人もいたようです。
悪い場合には、自分や我が子への要望を押しつけるだけでなく、
自分に話し相手がいないから、ストレスのはけ口がないから、
その相手を担任にしてもらおうと言わんばかりの罵倒や話の筋が通らない文句があったりします。
「この親と1,2年は付き合っていかないといけないのか…」
という思いは相当負担になります。
同僚の教員との関係性と教員の病休

最後に、同僚教員との関係性の関連から、病休について考えていきます。
はっきり言ってしまいますが、私の経験上、
職場の教員同士の仲の良し悪しで病休に入る人が大きく増減すると思っています。
同僚の教員の影響
今まで見てきた病休の要因も、
教員同士の仲がよかったりフォローし合える関係性ができていれば、
悩みを打ち明けることができ、だいぶ気持ちを保つことができます。
(それでも、だましだまし何とかやっているという状態ではあるのですが…)
逆に、教員同士の仲が悪かったり、協力体制が取れていなければ、それだけで負担に感じます。
保護者や児童生徒のことで助けてもらえず、気持ちが病んでる中で無理して勤務を続けた結果、
病休に入ってしまいます。
小中学校は学年単位で動くことが多く、
中学校よりも学年の学級数が少なくなる小学校は特に、
学年主任との関係で勤務のしやすさが大きく変わります。
(かくゆう私も学年主任が大きな原因で続けられませんでした。)
管理職や同学年の教員
管理職が間に入って改善を図ってくれればいいのですが、
事なかれ主義なのか、あえて触れない場合が多いのではないでしょうか。
(それが病休や退職のリスクがあると分かっているにも関わらず。)
それどころか、辛くて今にも辞めそうな状態なのに、
「ここで諦めるともったいない」
「他の仕事と比べると弱音を吐いている場合じゃない(←教員しかやってこなかった人に限って言ってくる)」等、
“お前が変わればいい”という理屈で言ってきます。
原因を作っている学年主任の行いを知っているにも関わらず。
学年主任だけでなく、同じ学年を担当になった教員や同じ教科を担当する教員の影響も大きいです。
ただ単に考えが合わない程度ならまだいいのですが、
陰口を叩いたり、仲間はずれにしたり、人を見下したような言動や行動をするような人もいます(本当に子どもと変わらない!って思うほどに)。
そんな人を無視して仕事ができればいいのですが、
業務上絶対に関わらなくてはならないため、
否が応でもコミュニケーションを取らなくてはならないのです。
そして仲が悪いことで足並みが揃わずコミュニケーションもうまくとれないことで、
一般企業の職場内いじめと大きく違うのが、
「児童生徒に迷惑をかけてしまう」
「子ども達のためにならない」と、
子どもへの責任感から自分を責めてしまう、適当に流すということができない、
という枷があることです。
児童生徒へのあるべき対応とのギャップを感じてしまい、気持ちが折れてしまいます。
筆者の経験上、児童生徒への責任感の強い人ほど、
同僚の教員ともめ事を起こしちゃいけないと思い、我慢されている気がします。
まとめ(筆者主観)
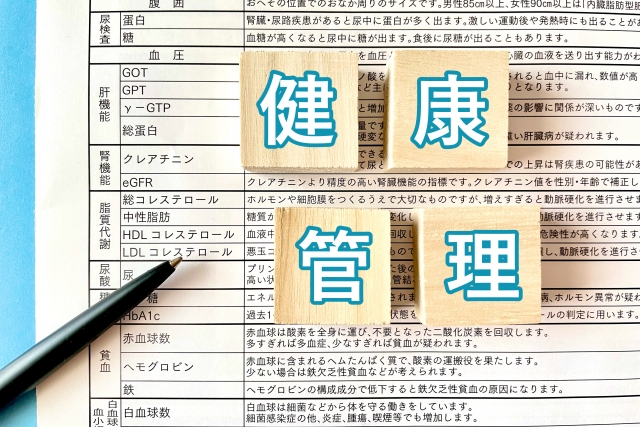
細かな違いは職場によってあると思いますが、
教員をしている方には少なからず共感していただけることかと思います。
元々教員になろうとしている方々は、
長時間労働や児童生徒対応の難しさも予め覚悟の上で務める人が多いです。
労働環境の悪さをはねのけられる人も多いです。
それを打ち砕いてしまうのが、皮肉なことに、同じ?志をもった同僚の教員でもあるのです。
教員は「何のために働いているんだっけ」という
アイデンティティの問題は起こりにくいと思っています。
それが営利企業と比べての良さだと思っています。
子どもの未来をつくっているという意識は確かにやりがいを感じます。
しかし、そのやりがいが感じなくなってしまうほど、
職場環境が悪かったら、反動が大きくなってしまうというのも分かりました。
「子どものため」という意識は、労働苦を跳ね飛ばす希望である一方、
同僚仲に左右される諸刃の剣になり得ることも。
教員でも退職代行サービスを使う道がある
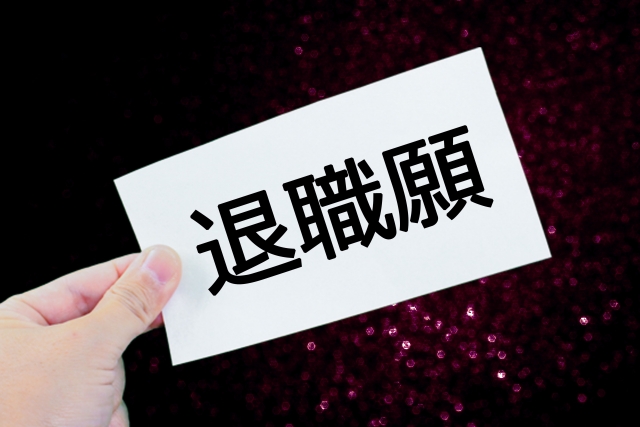
病休に入る教員が多いことと比例して、
病休に入る一歩手前で踏ん張っている教員もいらっしゃると思います。
それではなく、毎日辛くて辞めようと思っている人も多いはずです。
ただ、先にも書きましたが、
「一年間勤めないと児童生徒に迷惑がかかる」
「今辞めたら退職までの間、他の教員から白い目で見られてしまう」と思って、
辛い体に鞭打っている状態でしょう。
もし、教員をすぐに辞めたいけど、子どもや教員との関係性があって辞職を言い出せない、
という状態でしたら、
「退職代行」というサービスを使うといいでしょう。
職場に行かず、退職までの手続を行ってくれます。
退職代行とは、社員本人に代わって会社に退職の意思表示をしてくれるサービス
引用元|みんなの採用部
今は何社かが退職代行を行っていますが、代表的なものを一つご紹介します↓↓
「退職代行ガーディアン」は、東京労働経済組合が運営しているサービスです(東京の人しか利用できないわけではないですよ)。民間企業が運営しているサービスよりも安心して申し込める人が多いのではないでしょうか。
料金も29,800円(他と比較しても良心的な値段)で依頼することができ、他の退職代行サービスでみられるような追加料金もないです。電話だけでなく、LINEで相談できることもメリットです。
(パワハラや長時間労働で体を壊した等の、会社都合で退職を考えている場合は、その旨事前にご相談することをおすすめします。)
最後に|誰かに相談をしたい先生へ
休職することをためらってしまう人もいらっしゃいます。
そのような人に向けて、肩の力を抜いていいんだよ、という気持ちで書いた記事があります。
よければこちらもご覧ください。
自分の辛さをわかってもらいたい、
いったん職場を離れて心を休めるべきか専門家に相談したい。
という人は、
オンラインクリニック「かもみーる」をご利用ください。
心療内科の先生が、優しく話を聞いてくれます。
あなたの状態によっては、診断書も書いてもらえます。
もし、顔を合わせた相談が苦手、抵抗があるという人は、
こちらのチャット相談サービスをご利用ください。
(こちらはココナラの無料会員登録が必要になります。)
あなたの辛い思いを3日間(チャット5往復分)、
チャットでお聞きして受け止め
いっぱい共感して
少しでも気持ちが楽になるように励まします!

今辛い思いをしながら働いている人が、少しでも少なくなれば幸いです。
皆さんどうか無理なさらずに。
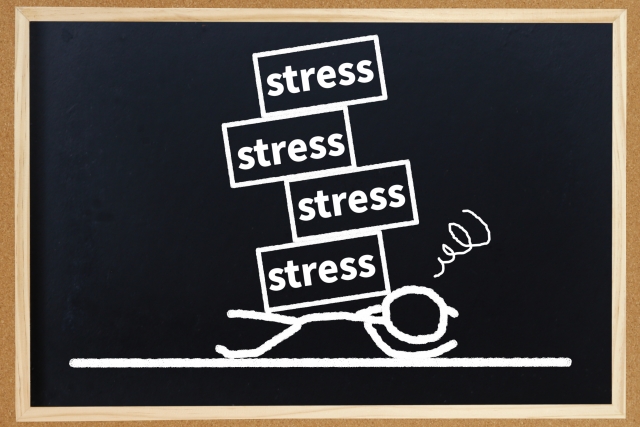



コメント