2010年くらいから、日本の子どもの貧困ということをよく聞くようになりました。
それに伴って、教育系のNPOの存在が徐々に広まってくるようになりました。
NPOが行っていることとして、
子どもの居場所支援や
学習支援といった活動がメディアでも取り上げられるようになりました。
学習支援事業とは、
経済的に困窮している家庭の児童生徒を対象に
無料で勉強を教える学習会を開催する事業のことです。
子どもに勉強を教える人の多くは無償で行っている場合が多いです。
営利事業ではないので、授業料をとることができません。
なので、お金のやりとりはほとんどありません。
(交通費をだしてもらうくらい。)
学習塾でアルバイトをすればお金がもらえるのに、
なぜ無償で勉強を教えてくれる人がいらっしゃるのでしょうか。
そんな学習支援事業の実態と
無償で関わってくれる人の様子を、
実際に学習支援教室を運営していた筆者がお伝えします。
教育系のNPOについては別記事でも紹介していますので、
合わせてご覧ください。
そもそも学習支援ボランティアとは

学習支援ボランティアとは、
利用する児童生徒が無料で参加する学習支援教室(学習会)で、
勉強を教える講師として携わる人のことです。
塾などで勉強を教えるときは学習’指導‘と言ったりしますが、
社会課題解決の場面などではよく’支援‘という言葉を使うので、
学習支援は社会課題の解決や子どもを支える
といった意味合いが含まれています。
とはいえ、使われ方や解釈は
その現場や運営元によっても異なります。
また、ボランティアと名前がついていますが、
有償で関わるボランティアの人もいますし、事業によっては有償になります。
基本的に無償で関わる人が多いです(交通費はだしてもらえたりします)。
学習支援の目的
学習支援は、主に子どもの貧困問題の一つの手立てとして行われることが多いです。
(不登校の児童生徒の学習機会確保で学習支援を行うこともありますが、
ここでは貧困対策の学習支援を軸に話を進めていきます。)
その目的はいくつかありますが、
主なものを3つ挙げます。
学力の向上
経済的に不利な状況にある子どもは、
学習塾にも通えなければ、家事をする必要があったり、中には家族の世話をしている子どももいます。
平均的な同世代と比べて不利なことが多いです。
その影響で学校の授業についていけない状態がでてきます。
(学習時間の確保や、日中の集中力などにも影響してきます。)
そこで、いくつかある貧困状態になってしまう理由の一つ
学力に焦点を当てて、貧困の連鎖を断ち切ろうという試みです。
同世代の他の生徒と比べて、学習の機会格差が広がってしまうのを防ぎ、
学習する時間と場所を提供する狙いがあります。
相談できる場所の提供
経済困窮の家庭は、社会的つながりも乏しかったりします。
頼れるところが多くないのも現状です。
子どもにとっても頼れる場所、頼れる人が少なくなります。
誰かに辛さを話したい子どもにとって、大きなストレスです。
それを解消するのが、学習支援教室であり、学習支援ボランティアになります。
生徒の悩みに寄り添って心のケアをするのも、学習支援ボランティアの大事な役割になります。
ロールモデルの存在
子どもにとって身近な人の生き方や職業は、自分の将来を考える大きな要素になります。
多くの人とふれあう機会があれば、自分の将来の選択肢が増えます。
しかし、生活困窮家庭の児童生徒は、ふれあう大人の数が少ない傾向にあります。
保護者と学校の先生くらいしか大人を知らない場合もあります。
自分の保護者の生き方しか知らないと、自分の生き方を自分で選べると思えなくなってしまいます。
それを解決する一つとして、学習支援教室でいろいろな大人や学生とふれあうことが挙げられます。
多くの大人の存在を知ることで、将来の選択肢を増やしたり、努力することで自分の進む道が選べることを知れます。
将来に希望をもてるきっかけになります。
学習支援教室の形態
学習支援教室の内容
小規模の場合、生徒がワークなどの教材に取り組んでいて、
自分では解けない問題を学習支援ボランティアに質問する、
という場合が多いです。
規模が大きくなると、
生徒2,3人に学習支援ボランティアが1人付いて個別対応をすることもあります。
また、一斉授業のように、
生徒10人くらいを前に、学習支援ボランティアが講義を担当する形式をとっていることもあります。
開催時間
開催の日程は規模や団体によってバラバラです。
週1回開催のところもあれば、
毎日開催をしているところもあります。
時間も2,3時間開催のところもあれば、
半日開催とたっぷり時間をとるところもあります。
開催場所
開催場所も運営団体によってバラバラです。
自前の部屋で開催するところもあれば、
公共施設を借りて開催しているところもあります。
学習支援ボランティアとして大学生も社会人も関わっている

学習支援ボランティアとして関わっている人には
大学生だけでなく、普段仕事をしている社会人もいらっしゃいます。
それだけでなく、定年退職した人もいらっしゃいます。
平日は児童生徒も学校があるので、
学習支援教室の開催は夕方から夜になることが多いです。
そのため、日中に大学の講義や仕事があっても、
夜に参加しやすいことが多いです。
なぜ無償で勉強を教えるのか
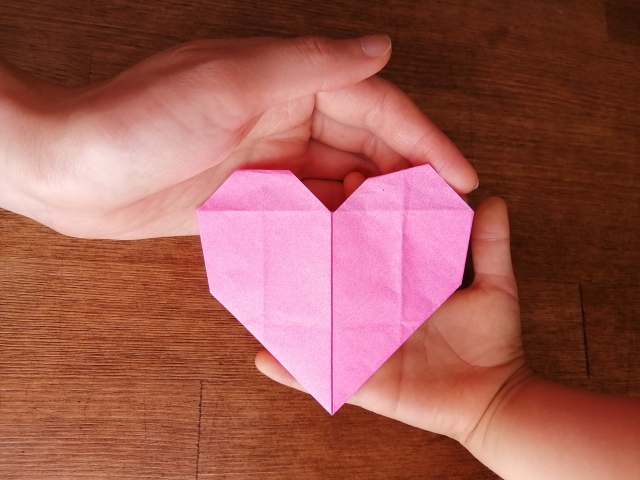
冒頭でも書きましたが、学習塾で講師をすればバイト代をもらうことができます。
それをせずに無償で勉強を教えてくれるのはなぜか。
もちろん、理由は人それぞれあります。
ここでは、筆者が現場で職員として働くなかで、
ボランティア参加してくれた人の志望動機を2つ紹介します。
ある大学生の場合
学習支援ボランティアにはたくさんの大学生が参加してくれています。
その中の一人で、大学合格後、早い時期から関わってくれる学生がいました。
その人は、ご自身もひとり親家庭で過ごし、裕福な家庭ではなかったそうです。
しかし、自身の努力もあり、有名大学に合格しました。
その経験から、自分と同じような立場の子の力になりたいと思ったそうです。
無償でも子ども達の力になれているという実感があるので、
関わり続けたいと言っておられました。
ある社会人の場合
学習支援ボランティアには社会人もいらっしゃいます。
その中でも、毎週同じ回に必ず参加してくれる人がいらっしゃいました。
その人は、娘さんが入試を終えて、
ご自身も中学生の受験勉強の力になりたいと、ボランティアに参加してくれました。
それをきっかけに、子どもの貧困に興味をもってもらうようになりました。
勉強を教えるだけでなく、社会課題に解決に力を使いたいという目的に変わられました。
現場経験者から伝えたいこと

学習支援教室は、小さな組織が小規模でやっているものもあれば、
大きな組織が中~大規模でやっていものまで様々あります。
どこで関わることになっても、それぞれの良さがあります。
もしやってみようか迷っている人がいたら、
直感で選んで始めてみてもいいでしょう。
どこで関わろうとも、そこに来ている子どもに愛着をもってきます。
また、運営者の立場からすると、
いろいろな人がいてくれる方がいいです。
子どものタイプや悩みはそれぞれなので、
相性のいい人を選べる状態は嬉しいです。
また、何か子どもの助けになる活動がしたいという人には
不登校の生徒の家庭教師をしていた筆者の経験を書いた記事があるので、
そちらもご覧ください。
最後に|今後の展望

学習支援ボランティアは大学生や社会人、年配の人まで
多くの人に支えられて成り立っています。
皆熱意をもって関わってくれています。
こういう社会課題は行政が解決するべきもの、と考える人もいるでしょう。
それは一部正しいです。
そのために税金をとられていますからね。改善の必要はあります。
ただ、どんな施策を打ち出そうと、行政の支援からもれてしまう人はでてきます。
平等主義や前例、法律を根拠にする行政だと対応が遅くなるのも仕方ありません。
そんな中、NPOなどの民間セクターが、社会課題に向き合う必要性は
今後増えてくると思います。
行政よりも柔軟に動ける利点を活かして、
セーフティネットを築く立役者になるはずです。
そんなとき、どのような形であれ、皆さんの力をお貸ししてほしいです。
学習支援ボランティアもその一つです。
行政だけに頼らない、助け合える社会を築ければと思っています。
学習支援ボランティアの話をもっと聞きたい!
教育系のNPOに勤めることも考えている!
という人がいらっしゃいましたら、
ココナラで相談サービスを行っていますので、
ぜひこちらをご利用ください。
ココナラの使い方簡単3ステップ(タップ/クリックすると詳細が開きます。)
ステップ1|会員登録
・メールアドレスを入力し登録用URLを発行
・会員情報を入力
(必須)ユーザー名、生年月日
(任意)性別
※決済はコンビニ払い、クレカ払い、キャリア払い等可能
ステップ2|サービス検索
・ココナラの検索で「きくみち」と入力して検索してください。
カテゴリーは「恋愛相談・悩み相談・話し相手」になります。
(複数表示される場合は「転職を考え始めた先生のキャリア相談にのります」をお選びください。先生でない方からの相談も受け付けております。)
ステップ3|サービス購入
・「サービス購入」後に取引画面の購入ボタンを押下してください。取引メッセージに移動します。





コメント