国家公務員試験といえば
法律や経済の専門知識を必要とする試験がメジャーです。
しかし、受験人数は少ないですが、
いくつかのマイナーな科目も存在します。
工学や統計学なら内容が想像しやすいですね。
しかし、人間科学という科目がありますが、
科目名だけだとどんな内容なのかわかりません。
しかも、受験生が少ないこともあり、
科目の情報がほとんどありません。
今回は、国家公務員試験の中でも、実際に私が受験したことのある
「人間科学」という試験区分について紹介していきます。
(だいぶ前の情報が含まれるので、実際に受験する方は最新人事院の情報をご確認ください。)
※法務省専門職員の採用試験とは別物ですので、ご注意ください。
国家公務員については、別記事でも紹介していますので、
こちらも合わせてご覧ください。
なお、試験の概要は他のサイトでも詳細を書いているので、
ここでは私個人の体験談を中心にご紹介していきます。
また、5~10年前の情報(現在2023年6月)になるので、
今は適用されていないものがあるかもしれません。
国家公務員試験を受験される場合は、くれぐれもご自身で最新の情報をご確認ください。
(試験ごとの受験者数や受験日程は数年間で驚くほど変わっていました…)
国家公務員試験と並行して、一般企業への転職活動も視野に入れている大学院生の人は、
こちらの大学院生専門の転職エージェントのご利用をおすすめします。
アカリクは、実際に私が利用して、とてもいいサービスだと思いました。
「利用者の選考突破率8割」という実績も魅力的です。
国家総合職「人間科学」区分とは
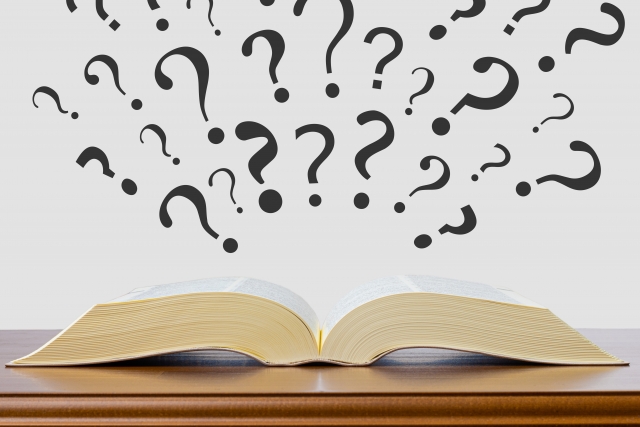
国家公務員試験は、
(行政分野に限りますが、)総合職試験と一般職試験に分かれます。
一般職試験は他分野から幅広く出題されますが、
総合職試験は専門分野を絞って深い内容の知識が問われます。
「法律」「経済」といった専門分野がメジャーになり、
その試験に受かった人を多く採用する傾向にあります。
そんな総合職試験の中に「人間科学」というマイナーな試験区分があります。
採用人数も少ないです。
総合職試験には、「院卒者試験」と「大卒者試験」に分かれますが、
人間科学分野はどちらにも共通して実施されています。
国家総合職、人間科学区分の試験内容
人間科学の出題内容ですが、大きく分けて2種類あります。
1つは心理学分野、
もう1つは社会学・教育学・福祉の複合分野です。
国家公務員試験は、1次試験→2次試験→官庁訪問→内々定、という手順で進みます。
1次試験の内容
1次試験ではマークシートの選択問題になります。
人間科学の選択問題は合計40問出題されます。
出題形式は3部制になっています。(この他、一般教養に該当する基礎能力試験もあります。)
Ⅰ部は両分野共通で5問出題されます。
Ⅱ部は2つの分野から1つを選択して、それぞれ15問の出題に解答します。
Ⅲ部はとっても細かく、14科目の中から4科目を選択し解答します。
1科目5問なので、Ⅲ部は合計20問解答します。
科目はそれぞれ、心理学、社会学、教育学、福祉をさらに細かく分けて出題されます。
選択問題は合計40問です。
試験の出題形式の影響もありますが、
心理学を勉強してきた人は心理学分野を、
社会学や教育学や福祉を勉強してきた人は、社会学・教育学・福祉分野を選択します。
Ⅲ部では心理学-福祉という組み合わせの科目を選ぶことはできますが、
勉強する範囲が増えるので普通は選ばないです。
心理学は本当に難しそうで大変なので、心理学だけで手一杯になりそうです…
ちなみに、私は大学、大学院と教育学、教育社会学に携わってきたので、
社会学・教育学・福祉の複合分野を選びました。
実際の試験でも社会学や教育学は馴染みがあったので解きやすかったですが、
福祉は馴染みが少なく、分からないことも多いので、
なるべく得意分野で正答することを考えていました。
公務員試験の勉強方法については、こちらの記事もご覧ください。
2次試験の内容
1次試験に合格したら、次は2次試験で筆記の選択問題が出題されます。
人間科学の筆記試験は、6題ある中から2題を選択します。
(この他にも、面接と、政策課題討議(院卒)または政策論文(大卒)があります。)
その内訳は、
- 心理学2題
- 社会学1題
- 教育学1題
- 福祉1題
- 社会学・教育学・福祉の複合1題
となっております。
私は当然、社会学、教育学を選びました。
人間科学区分を合格した後に入省できる部署

2次試験も合格し、晴れて次のステップに進むことになった場合、
最後の難関「官庁訪問」に挑むことになります。
官庁訪問では、自分が希望する省庁に何度か足を運んで省庁の面接を受けることになります。
2次試験で面接しているのは人事院で
公務員としての採用していいかどうかを見極めている一方、
官庁訪問では省庁に適しているかどうかを見極めている
といったところでしょうか。
官庁訪問をする前に
ちなみに、私は2次試験合格後、その年の官庁訪問はしませんでした。
2次試験に合格すると、合格者名簿というものが作成し、
2年後の官庁訪問まで顔パスで参加(1,2次試験免除)することができます。
それを利用して、省庁以外の仕事を、とりわけ学校現場を経験した後に
文科省に入省しようと考えていました。
今タイムマシンで当時に戻れたら絶対に止めていますが笑
また余談ですが、私の時は国家公務員試験2次合格の知らせは葉書で届きました。
これは大切に保管することをお勧めします。
私の場合、大学院の修了旅行の際にHISを利用したのですが、
割引キャンペーンの一環で、国家総合職合格者が割引になるというメニューがありました。
その証拠として葉書を提出したら見事旅行代金が割引になりました!
話はそれましたが、官庁訪問の話に戻ります。
人事院が試験区分によって省庁ごとの採用があるかどうかのお知らせをしてくれています。
これを見て、自分が入省したい省庁が受付をしているかどうかを確認します。
人間科学は法文系に含まれるので、
「法律や経済といった試験区分の人達と合算して○人採用します」
という省庁が多いです。
必ず募集がある省庁
確実に人間科学区分の受験生を採用するとしているのは、
法務省と厚生労働省です。
教育学の知識があるから文部科学省に入省できる!ということではないようです…
私の代やその前年などは、文科省に採用された人はいました。
いたとしても1人だったと思います…
あとは、内閣府や環境省でも1人いたかもしれません。
内閣府は仕事内容が多岐にわたるため、また青少年問題や認定こども園の施策もあって、
人間科学受験者で希望する人もいたんだと思います。
いずれにしても、国家公務員試験受験者(法文系)の大半は、
法律や経済を専門にする人達で、各省庁もそちらをメインに考えています。
人間科学受験者への期待はまだまだ小さかったです…
では、なぜ法務省と厚生労働省が専用の枠を設けて採用しているのか。以下で解説していきます。
人間科学区分で合格した国家公務員|法務省

法務省と聞くと何を思い浮かべるでしょうか。
とても重要な省庁であることは間違いないですが、
どういう業務をしているか分からない人もいるのではないでしょうか。
実際に法務省は、財務省や外務省などと同じように一流官庁と呼ばれ、
省庁の中でもランクは高いです。
あと、庁舎に入る際には、入り口で手荷物検査を受けます。
厳格なイメージそのままですね。
(文科省は駅の改札機みたいにカードをかざすだけで入れます。)
少年院
そんな法務省ですが、実は少年院を管轄しています
(その他刑事施設も管轄しているのですが、このブログでは教育に興味を持たれている方に多く見てもらっているので、少年院を中心に紹介していきます)。
詳しい説明は省きますが、人間科学受験で入省すると少年院に関わる仕事を行います。
府省別採用予定数では、法務省の矯正局と保護局が人間科学枠で募集をしています。
矯正局、保護局
矯正局では、少年院に入院している少年への指導監督、教育をすることになります。
また、同じ役割をする職種として、法務省の職員として募集している法務教官という仕事があります。こちらも国家公務員の1つです。
対して保護局では、少年院などの施設から一般社会に出られるまでのサポートをする仕事になります。
それらに加えて、時々大元の法務省に出向くこともあるようです。
なので、現場と事務の間の役割ということになります。
私が採用説明会に参加したときは、法務省の職員の方から「まずは矯正局(の職員として勤務)だと思って」と言われました。
人間科学区分で合格した国家公務員|厚生労働省

新型コロナウィルスの影響もあり、厚生労働省がテレビに出てくることも多くなりました。
福祉を勉強されてきた方の中には、保健医療、介護、年金問題を解決するため厚労省に入りたい!と思っている方もいるのではないでしょうか。
そのために、人間科学で受験される人もいるかもしれません。
ただ、人間科学枠で厚労省に入省した場合、職業安定・雇用の部署に配属されます!!
当時の採用説明会でも「地方の労働局やハロワ(職業安定所)に出向したりするよ。他の部署で採用された例は知らないなあ。」と現役職員に言われました。
私の中では、人間科学になら保健や福祉が適しているのでは?とも思うのですが、
他の専門職で医療やそれらの部署への配属になるのか、イメージと違うと思われました。
終わりに|国家公務員試験の受験方法の増加

国家公務員も教員と同じで、年々受験者数が減っていて、人気がなくなっているようです。
東大生も国家公務員ではなく、ベンチャー企業を選ぶ人が多いのだとか。
その影響もあってか、いろいろな試験種が出てきましたし、社会人枠の受験機会も設けられました。
さらに、一般の転職サイトでも中途入社の募集広告が出ているほどに。
人事院も国家公務員離れに危機感を持ってきているのかもしれませんね。
公務員試験勉強と就活を同時に進めたいという方は、
こちらの大学院生専門の転職エージェントのご利用をおすすめします。
アカリクは、
アカウント登録を含め、無料ですべてのサービスを利用できます。
大学院生専門ということもあり、大企業、高待遇の求人を多く紹介してくれます。
忙しい院生に代わって、希望に沿った求人を選んでくれます。
企業の評価ポイントに基づいてES添削や面接対策を実施してもらえます。
「利用者の選考突破率8割」という申し分ない実績を持っています。
また、公務員試験を受けるかどうか
気軽にチャットで相談したいという人は、
こちらの相談サービスをご利用ください。
(こちらはココナラの無料会員登録が必要になります。)
あなたのお悩みを3日間(チャット5往復分)、
いっぱい聞いて
あなたに最適なキャリアが形成できるよう
精一杯アドバイスします!

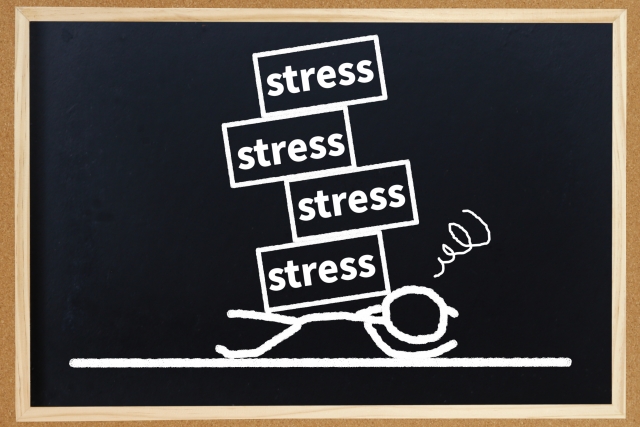

コメント